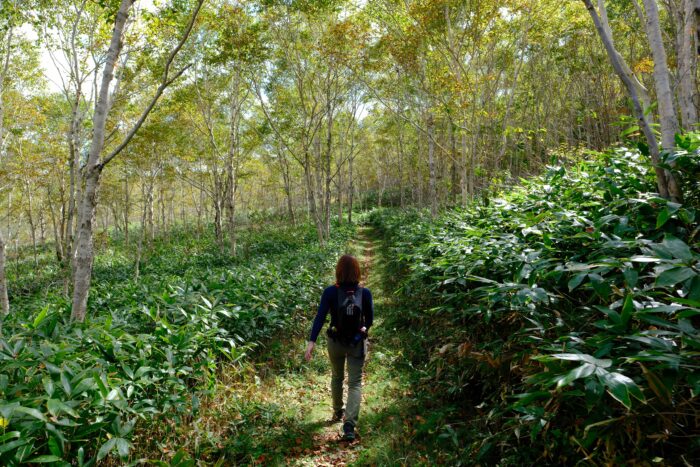奥さんとふたりで紅葉の野反湖に出掛けてきた。早朝に自宅を出て、午前中に湖畔を一周した。秋晴れの青空が広がる気持ちの良い一日だった。下の写真では紅葉らしいシーンを切り取っているけれど、富士見峠から眺める白樺はまだまだこれから紅葉といった雰囲気。写真を確認すると、昨年は10月14日に、一昨年は10月8日に野反湖を訪れていて、どちらの日も紅葉はほぼピークだったようだけれど(その前の年は10月17日で、紅葉は終わりかけ)、今年のピークは10月20日頃まで遅れるかもしれない。20年くらい前は10月初旬が紅葉のピークで、20日を過ぎると木々はすっかり落葉していたように記憶しているのだけれど。